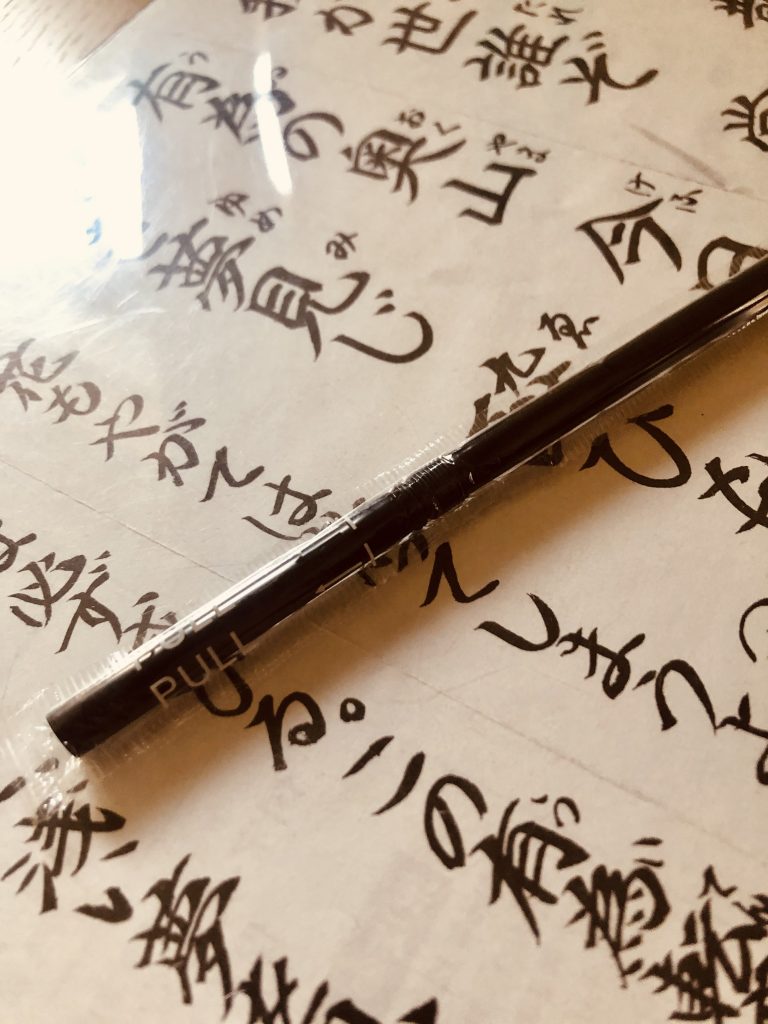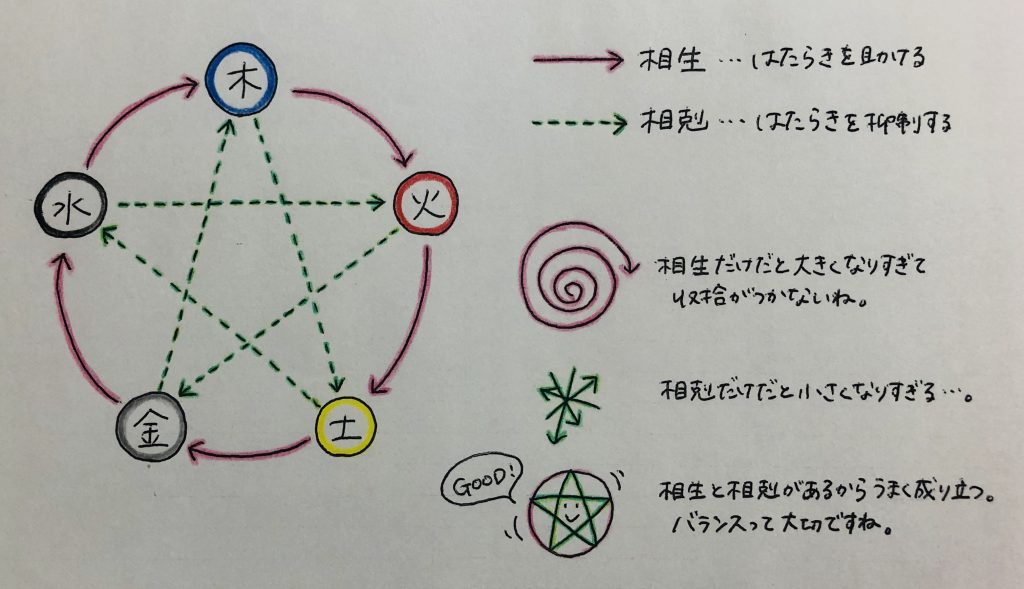皆さんは映画が好きですか?
凄いですね鬼滅○刃。老若男女問わず人気で、日本の?歴代興行収入第一位に!
ただひとつ個人的に引っかかることがありましてね、少しばかり低年層には刺激が強過ぎやしません?とは思うんです。視聴者にもよるでしょうけども
数話、話題の為という口実で見ましたが、話によっては人や鬼がバッサバッサと。。。
ストーリーとして仕方ないんですが、描写がまんま過ぎて。に加えて、日本アニメは世界的にも高クオリティがありますから、音響による効果もリアルな印象。
ですが、それを緩和させる?くらいの感動ストーリーや、笑い、描写もあり、それが人気の要因なんでしょうね。
過激な描写による緊張、かたや感動、笑いによる緊張の緩和。
緊張と緩和の繰り返しの中、先々のストーリー展開が見るものを、、、、
とまぁ、あんた誰やねんというくらい書いてますけど。苦笑
これもまた個人的な〜ですが、こういった緩急の強めな物事がウケやすい要因として、
大きく、大きく、大きく
人間という生き物で見ると、
生存していく中で心身の緊張度合いが年々高くなっているんだろうなぁと。
このご時世なんて特に、情報に溢れ、目に見えない恐怖、不安。。。
そこに事物、他者からの刺激でさらに心身は緊張!
が、こういう作品などの感動や笑いで緩解。*緩解要因は個それぞれ
その緩解が平素の緊張感からの解放という心身の安堵に繋がりさらにそれを求めて、うんぬんカンヌン
 この冬のわたし的緩解、解放はこのコップで生豆より挽き入れた珈琲をいただくこと。至極のひととき。
この冬のわたし的緩解、解放はこのコップで生豆より挽き入れた珈琲をいただくこと。至極のひととき。
まぁ、長ったらしくダラダラと書いてますが、
このアニメの作中にもあるように
「全集中の呼吸」
全集中はさておき、呼吸の方です。
上述した緊張や緩和ですが、これに大きく関わるのが呼吸なんです。
この緊張と緩和(呼吸)の過不足、時間経過によって体調って大きく変わり、
一部では原因不明の症状となり、世間一般的によく言われる自立神経がどうのこうの、、、という状態になったりならなかったり*諸説色々あります。
では、呼吸、自立神経ってなんぞ?
っていうのはいつものwiki先生を見ていただき「https://ja.wikipedia.org/wiki/自律神経系」(要は、意識して動かせない、生存し続けるために自動で動いてくれている神経なんです、呼吸はその神経によって〜ってことですね。ほんま?笑)
では、本当に意識して動かせないのかというと半分ホントで半分ウソですね。
限度はあれど意識的に呼吸を止めることもできますし、速く細かくや遅く深く呼吸するといった調整ができるんです。
去年2019、9月にも同じ治療家の池田先生のブログ内にありましたが、
- 「息を吐くと、副交感神経が優位になり、筋肉や血管がゆるんで血液の流れが良くなります。血液の流れが改善されると、体温が上がります。
- 呼吸は、自分で意識して、速くしたり遅くしたりすることが出来ます。
- 血圧が高かったり 低かったり、動悸がしたり、体温が高すぎたり 低すぎたりした時にも、吐く息を中心にしてゆっくり呼吸をすると、体温や脈のリズムが整ってきます。
- 日ごろ、多くの方の身体を診させていただいて強く感じることは、ストレス社会を生きる現代人の方たちの多くが、「吸う息」ばかりになっていたり、「息が止まってしまっている」ということです。
- 吐く息を中心にした呼吸は、身体や心の緊張をゆるめ、全身に活力を与え、自律神経を安定させます。」
と書かれているように、
呼吸のコントロールによって、日頃からもっと体を簡単にケアできるのでは???
はたまた、鬼滅○刃の竈門炭○郎や我○善逸、嘴平伊○助のように基礎体力が劇的に上がり強く逞しく、JOJO○奇妙な冒険のように波紋(技の一種です)を使えるように。。。。
など、結構意識していると呼吸に関して取り上げられています。
さぁ、マスクばかりで息苦しい環境がまだまだ続きますが、
外せる時にはしっかり息を吐いて、吸うて、全身にエネルギーを送って、不要なものを吐き出してというイメージでやってみても良いかも!?
(※循環器、呼吸器の既往、疾患、大病の既往のある方は“十二分に気をつけて”呼吸をしてください。)
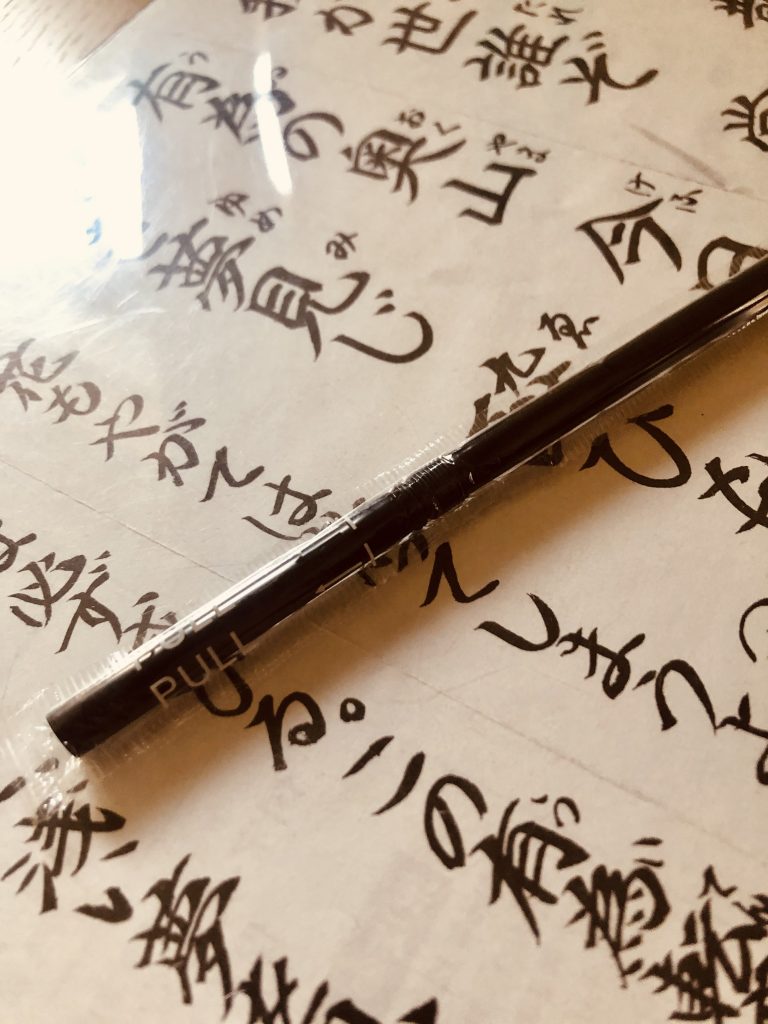 呼吸方法の一つとしてストローを使う方法を昔、漢方老師より教えてもらいました。
呼吸方法の一つとしてストローを使う方法を昔、漢方老師より教えてもらいました。
息を自然に吸って、ストローから力まず、ゆっくりと息を吐き出しを繰り返す。ポイントは力まず、無理せず。
良い年の瀬をお過ごしください、また来年もよろしくお願いモ〜ゥしあげます。丑年なだけに
[治療家 矢野 慎也]