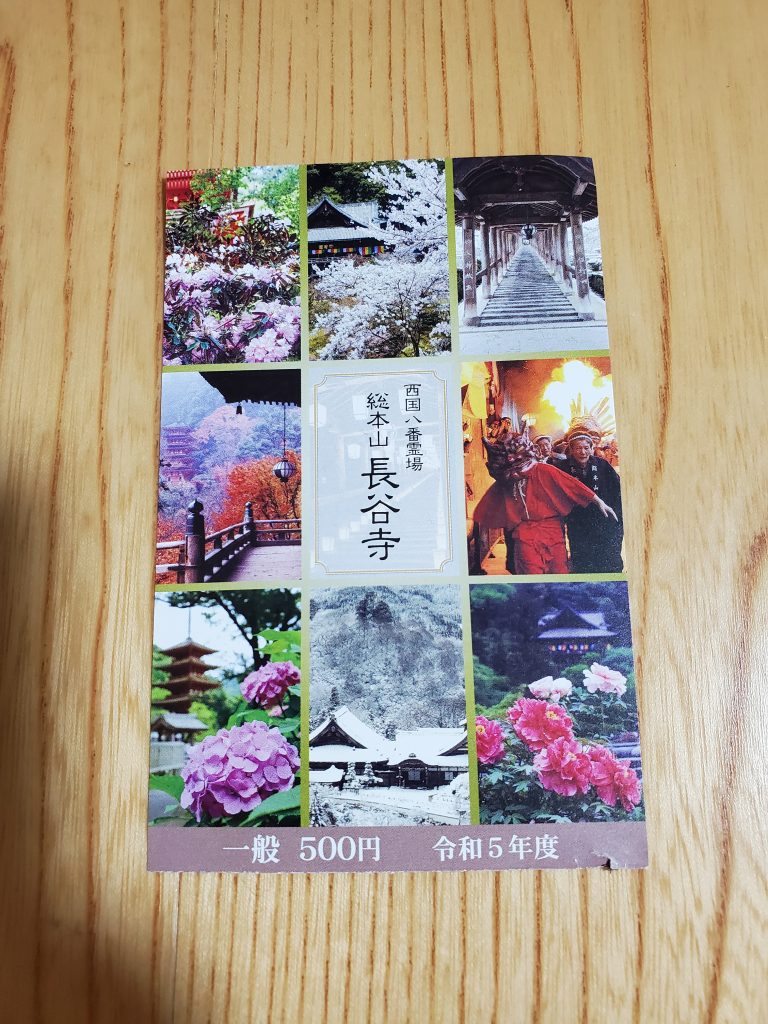鍼灸大仙堂のブログへようこそ♪
本日4月20日より二十四節気の暦では「穀雨」に入ります。
春の温かい雨が大地を潤し、穀物の成長を助けてくれる時期です。戸外を歩いていると、昨日の雨で植物や木々の輝きが一層増しているように感じました。農業をされている方は忙しくなる時期でしょうね。また、お庭がある方は雑草との戦いの時期でしょうか。
今年は5月5日までが穀雨となり、立春から始まった春の季節も終わりとなります。春の最後のシーズンを五感(目、耳、鼻、舌、皮膚)で感じながら、過ごしていきたいと思います。
【目・耳・鼻】
【舌・目・鼻】

【皮膚・目・舌・鼻・耳】
この時期、ご家庭で花や野菜を育ててみるのもいいですね。上記でご紹介した枝豆は、植木鉢でも簡単に育てることができて、収穫して食べることもできます♪日に日に成長していく様子を眺めるのはとっても楽しいですよ。オススメです!
昨年秋に収穫した枝豆を食べずに、乾燥させて今年用の種にしているものが手元にあります。もし、「育ててみたい!!」「食べてみたい!!」と思われる方には、先着10名の方々に差し上げたいと思っています。ご希望の方は大仙堂受付にて「枝豆の種希望!」と熊本宛に伝言をしてくださいね。
いい季節、五感をフル稼働させてお元気でお過ごしくださいね。
【治療家:熊本 和】
ps.昨年は5人の方に育てていただき、4人の方は大成功でした。お一人の方は残念ながら鹿に食べられて全滅してしまったそうです。