こんにちは。6月21日に二十四節気の夏至を迎えました。ご存知のとおり、太陽の南中高度が最も高くなり、昼の時間が最も長くなります。北半球では夏至を境に少しずつ日照時間が短くなっていきますが、夏の暑さはこれからさらに増していく季節です。
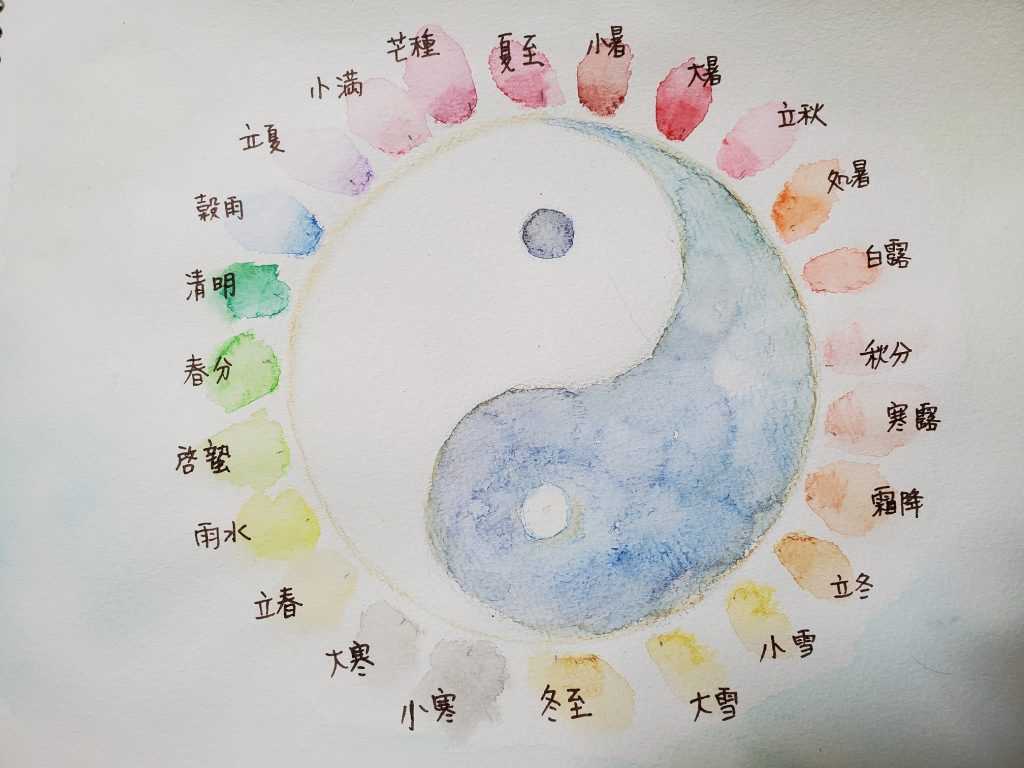
日本ではこの時期に梅雨も重なり、気温だけではなく湿度も高くなります。昨日、今日と天気予報の湿度をみてみると、なんと94%にもなる時間帯も・・・!!
日頃からカラダに湿気をため込んでいる私は非常にツライ時期でもあります。空気が乾燥している時はそうでもないのに、湿気が多くなるとゼロゼロゴホゴホとなってしまいます。暑いからと冷たいもの(←カラダの湿気の元)を多飲しないように気をつけていきたいと思います。

ところで、上の写真は6月のパリの街です。この夕暮れの時間がなんと22時過ぎ!!日の出から16時間あまりも明るい状態です。同時期の日本の日照時間は14時間半。この違いは位置する緯度によるもの等ですが、逆に冬至の頃はパリの日照時間は8時間、日本は9時間半。こういう違いはヒトのカラダにも影響してそうだなぁと思います。
そして、大変遅くなりましたが、先週6月19日に届いたお花を紹介させていただきます。

- ひまわり
- バラ(ピンク色)
- スプレーバラ(クリーム色)
- てまり草(緑色)
- アストランチア・スターオブビリオン(左下に垂れ下がっている薄黄緑色の花)
- カーネーション(白色)
- ベビーハンズ(右下の葉っぱ)
- マトリカリア(上に伸びている白い小花)
ギュッと豪華に花が集まっている周りにアストランチアやマトリカリアがあることで、涼風がそよいでいる感じがしていいなぁと思います。マトリカリアは結構長持ちするので私的にお勧めです。
最後にマトリカリアの花言葉を記します!「楽しむ心」、これ大切ですね。
【治療家:熊本 和】



























