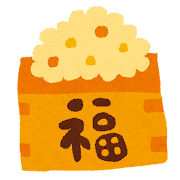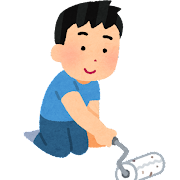今週も素敵なお花が届いております。
ラインナップ
- ダリア
- 紫陽花
- アルストロメリア
- アスター
- デルフィニウム
- マトリカリア


ダリア 
紫陽花 
アルストロメリア 
アスター 
デルフィニウム 
こんな感じでふと、この時期になるとはっきり日にちを覚えているわけではないのですが、「花まつり」というワードが頭をよぎります。
花まつり
ご存じですか?
花まつりはお釈迦さんの生誕祭。(4/8おめでとうございました🎉)
もともと灌仏会(かんぶつえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、降誕会(こうたんえ)などとも呼ばれ、仏教創始者であるお釈迦様の生誕をお祝いする仏教行事。
花まつりの由来は、お釈迦様が誕生したネパールの地ルンビニの花園を模した花御堂(はなみどう)という沢山のお花で飾り付けしたお堂でお祝いすることからその名がついたとか。
その花御堂内には灌仏桶と呼ばれるたらいのような器を置いき、うつわ内を甘茶(あまちゃ)で満たし、その中央に誕生仏が安置します。
参拝者はその誕生仏に甘茶をかけ、お釈迦さまの誕生日を祝います。
なぜ甘茶をかけるのか?
お釈迦さまが生まれる際、九頭の龍が天から現れお釈迦さまの頭から甘露の雨を注いだという言い伝えに基づくもので、灌仏会の「灌」とは水を注ぐという意味です。
そしてこのお釈迦さま(お話脱線です)
生まれた瞬間、東西南北に向けてそれぞれ七歩ずつ歩き、右手は天を、左手は地を指さし「天上天下唯我独尊」と唱えたと言われています。
ヤンキー漫画でよく見るやつですね、笑
漫画ではどういった意味で使われてるのかは不明ですが天上天下優雅独尊の意味がこちら!
『自分という存在は誰にも変わることのできない人間として生まれており、この命のまま尊い。』
世の中は、とかく何事にも優劣をつけ他人と比較して優越感に浸ったり、劣等感に陥ってしまいがちてす。
そうではなく君らひとり1人がオンリーワンやねん!
(世界に一つだけの花のフレーズ的、お釈迦さまが先ですね)
と生まれた瞬間に言ったんです。
という今週のお花から、花まつりネタ、格言へと続いて、
ふと過去の我が子の一枚を思い出しました。
↓↓

右手を天に向け(頭上)オンリーワンやでといわんばかりのポーズ。寝相。
残念ながら?生後2ヶ月半くらいで、なにもしゃべってませんが。
う〜ん、色とりどりの花の色のごとく今回のブログネタもとりどりとなりました。
長文駄文を最後までご覧いただきありがとうございます。
また大仙堂、ブログ内にて✋😁
[治療家 矢野慎也]